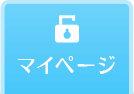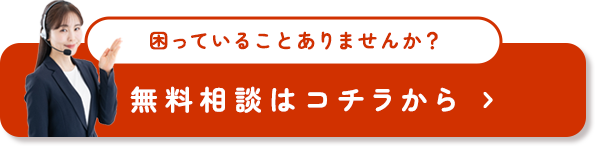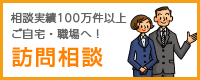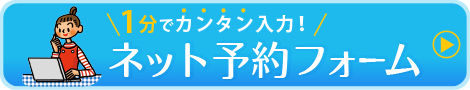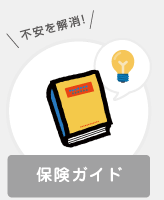カテゴリ:基礎知識
公的介護保険について

公的介護保険は、高齢化が進む現代の日本において、安心して老後を迎えるためにつくられた社会保障制度です。加齢や病気などで要支援や要介護状態と認定された高齢者に対して、必要な介護サービスを公平かつ、安定的に提供することを目的に運営されています。
被保険者は40歳以上のすべての国民で、要介護認定を受けた際に訪問介護や施設入所などのさまざまなサービスを受けられます。誰もが加入する可能性がある制度だからこそ、早めに公的介護保険について理解することが大切です。
本記事では、公的介護保険のサービス内容や利用条件、実際に支払う保険料などについて詳しく解説します。公的介護保険の申請方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
公的介護保険制度の概要

公的介護保険制度は、高齢化が進む日本において、介護を社会全体で支える仕組みとして2000年に導入されました。原則として40歳以上の国民が加入し、介護が必要と認定された場合は、訪問介護や通所介護、施設サービスなどのサポートが受けられます。
保険料は年齢や所得に応じて変動し、介護サービスを受ける際は、原則1割~3割の自己負担で利用できるのが特徴です。制度の目的は、介護者の家族の負担軽減や介護を社会全体で支えることにあり、介護の必要性が高まる現代社会において、とくに注目されています。
ただし、利用できるサービスには上限があり保険対象外の費用も存在するため、近年は経済的負担を軽減するために、民間介護保険と併用するケースも増えています。
公的介護保険で受けられるサービス
公的介護保険では、要支援、要介護の認定を受けた高齢者が、自立した生活を続けられるようにさまざまな介護サービスを利用できます。
以下の表に、主なサービス内容をまとめました。
| カテゴリ | サービス名 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 訪問系サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが自宅を訪問し、食事、排泄、入浴、掃除などの介助を行う |
| 訪問入浴介護 | 入浴設備を持ち込み、要介護者の方を 自宅で入浴させる | |
| 訪問看護 | 看護師等が医療的ケアや健康管理などを行う | |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が身体機能の維持やリハビリ指導を行う | |
| 居宅療養管理指導 | 医師や薬剤師、管理栄養士などが自宅を 訪問し、療養上の管理・指導を行う | |
| 通所系サービス | 通所介護(デイサービス) | 食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなどを受けられる |
| 通所リハビリ(デイケア) | 医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士などによる機能訓練を受けられる | |
| 短期入所系サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人施設に短期間宿泊し、日常生活支援や機能訓練を受けられる |
| 短期入所療養介護 | 介護医療院や病院などに短期間宿泊し、日常生活支援や機能訓練を受けられる | |
| 環境整備サービス | 福祉用具貸与 | 車いす、歩行器、介護ベッド、手すりなどをレンタルできる |
| 特定福祉用具販売 | ポータブルトイレ、入浴用椅子、腰掛便座などの購入補助(年10万円上限)を受けられる | |
| 住宅改修 | 段差解消、手すり設置、滑り止めなどの小規模改修(上限20万円) | |
| 施設系サービス | 特別養護老人ホーム | 常に介護が必要なひと向けで、生活全般にわたる介護サービスを受けられる |
| 介護老人保健施設 | リハビリを中心に食事、入浴、排泄などの介護を受けられる | |
| 介護医療院 | 長期療養と介護の両方を必要とするひとが対象で、生活全般にわたる介護サービスを受けられる | |
| 特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた介護付有料老人ホームやケアハウスなどの施設で、食事、入浴、排泄の介助や機能訓練などの 介護サービスを受けられる | |
| 地域密着型サービス | 地域密着型通所介護 | 定員19人以下の小規模なデイサービス事業所で、日常生活の支援や機能訓練、口腔機能向上サービスなどを 受けられる(要支援1・2のひとは利用不可) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 地域の小規模な施設で、通い、訪問、宿泊の3サービスを組み合わせたサービスを受けられる | |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症のある要介護者を対象に、少人数制の施設で介助や機能訓練を受けられる | |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が共同生活を送りながら支援を受けられる | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 地域の小規模な施設で、通所サービス、宿泊、訪問看護を受けられる | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問介護と訪問看護を組み合わせ、24時間365日体制で定期的な巡回や緊急時の対応を行う(要支援1・2のひとは利用不可) | |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間(午後6時~翌午前8時)に訪問介護員が自宅を訪問し、入浴、排泄、食事の介助や見守りを行う定期巡回と随時対応の2種類がある(要支援1・2のひとは利用不可) |
参考:公益財団法人 生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」
公的介護保険で受けられるサービスは、要支援と要介護の認定に基づき異なります。主なサービスには、自宅にヘルパーが訪問し、生活援助や身体介助を行う「訪問介護」、通所してリハビリや社会参加を行う「通所介護」、介護施設に入所して継続的な介護を受ける「施設入所」などがあります。
また、訪問看護や居宅療養管理指導、リハビリサービスも提供され、必要に応じて医療ケア、福祉用具の受給なども可能です。
公的介護保険のサービスが受けられる条件
公的介護保険制度では、利用者の状態に応じて「要支援1・2」(予防給付)と、「要介護1~5」(介護給付)の7段階の区分が設けられており、それぞれ利用できるサービスの内容や支給限度額が異なります。
以下の表に、要介護度別の状態の目安をまとめました。
| 介護度 | 状態の目安(心身の状況) |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的には自立しているが、日常生活の一部で支援が必要。転倒予防や軽度の介助など、一部の介護が必要な場合に適用される。 |
| 要支援2 | 身体機能の低下が進み、起き上がりや立ち上がりなど、部分的な介護が必要。日常生活で頻繁に介助を要することもある。 |
| 要介護1 | 日常生活の大部分は自立しているが、一部介助(排泄、入浴、掃除など)が必要。 |
| 要介護2 | 歩行や立ち上がりなどに介助が必要。日常生活に広く支援や介助が必要な状態で、認知機能に軽度の低下がみられることもある。 |
| 要介護3 | 日常生活の多くで介助が必要。認知症の症状が進行していることもある。 |
| 要介護4 | 重度の介護が必要な状態で、ほぼ全介助が必要。自力での移動や日常動作が困難になる。 |
| 要介護5 | 意思疎通も困難で、完全に寝たきりの状態。すべての動作で介助が必要になる。 |
参考:公益財団法人 生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」
要支援は軽度な介護予防が必要な状態で、日常生活に支障があるものの、まだ自立している部分が多い状態です。
一方、要介護は日常生活での支援が必要な状態で、身体的、精神的介護が必要な状態です。要介護度が高いほど、全面的な介護や医療的支援が求められます。
公的介護保険の加入はいつから?

公的介護保険は、年齢によって自動的に加入になります。65歳以上の人は「第1号被保険者」として全員が加入対象となり、原因を問わず介護が必要と認定されれば介護保険サービスを利用できます。
40歳から64歳までの人は「第2号被保険者」となり、公的介護保険の利用は医療保険に加入していることが前提です。この場合、がんや認知症など加齢に伴う16種類の特定疾病が原因で介護が必要になったときに限り、サービスが利用可能です。
特定疾病の種類は、以下になります。
| 1 | がん(末期) | 9 | 脊柱管狭窄症 |
| 2 | 慢性関節リウマチ | 10 | 早老症 |
| 3 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 11 | 多系統萎縮症 |
| 4 | 後縦靱帯骨化症 | 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
| 5 | 骨折を伴う骨粗しょう症 | 13 | 脳血管疾患 |
| 6 | 初老期における認知症 | 14 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 7 | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 8 | 脊椎小脳変性症 | 16 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方 」
保険料は40歳から医療保険と一緒に給料から徴収され、65歳からは原則として年金から天引きされます。加入の手続きは不要で、自動的に制度がはじまります。
将来的に介護が必要になったときに備えるためにも、加入のタイミングや対象条件を正しく理解しておくことが重要です。
公的介護保険の支給限度額と自己負担額

公的介護保険の支給限度額は、要支援や要介護度、サービスの種類に応じて設定されており、利用者が月ごとに受けられるサービスの上限額が定められています。
以下の表に、公的介護保険の1ヶ月あたりの支給限度額と自己負担額をまとめました。
| 介護度 | 支給限度額 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 1割:5,032円 2割:10,064円 3割:15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 1割:10,531円 2割:21,062円 3割:31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 1割:16,765円 2割:33,530円 3割:50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 1割:19,705円 2割:39,410円 3割:59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 1割:27,048円 2割:54,096円 3割:81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 1割:30,938円 2割:61,876円 3割:92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 1割:36,217円 2割:72,434円 3割:108,651円 |
参考:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
居宅サービスの支給限度額は、要介護度が高いほど増加します。要支援1の利用者は、介護予防のための軽度な支援を受けられ、要介護5になるとより本格的な介護サービスを受けられるため限度額が高く設定されています。
また、公的介護保険の自己負担額は通常1割ですが、所得が高い場合は2割または3割の負担です。 例えば、月額10万円の介護サービスを受ける場合、自己負担額は1割で1万円、2割で2万円、3割で3万円と上昇していきます。
自己負担が高額になった場合は?

公的介護保険では、月々の自己負担額が高額になった場合に備えて、経済的な負担を軽減できる「高額介護サービス費制度」の利用が可能です。高額介護サービス費制度は、所得に応じて自己負担の上限額があらかじめ設定されており、超過した分は申請後に払い戻されます。
自己負担の上限額は、住民税非課税世帯の場合は第1~3段階、住民税課税世帯の場合は第4段階として区分され、それぞれの上限額が定められています。
例えば、生活保護を受給している方などの第1段階の方であれば月額の上限は15,000円程度に抑えることが可能です。
さらに、同一世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合や、医療費と介護費を合算して一定額を超える場合には、「高額医療・高額介護合算制度」が利用でき、より自己負担額を軽減できます。 高額介護サービス費制度を利用するには、お住まいの市区町村の窓口で申請が必要なので、忘れずに覚えておきましょう。
公的介護保険と民間介護保険の違い

公的介護保険と民間介護保険は、介護に対する備えという点では共通していますが、仕組みや目的、サービス内容などが大きく異なります。
公的介護保険と民間介護保険の主な違いを、以下の表にまとめました。
| 公的介護保険 | 民間介護保険 | |
|---|---|---|
| 運営主体 | 国、市町村などの地方自治体 | 民間の保険会社 |
| 目的 | 国民全体の介護支援を公平に保障するため | 個人のニーズに応じた介護費用補填や生活支援 |
| 加入対象 | 原則として40歳以上の国民(強制加入) | 任意加入(年齢や健康状態によって制限あり) |
| 保険料の支払い | 40歳以上は医療保険とともに支払い | 保険契約時に決められた保険料を支払う |
| 給付の条件 | 要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けた場合 | 契約で定められた条件(要介護状態や特定疾病)を満たした場合 |
| 給付内容 | 要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けた場合 | 契約で定められた条件(要介護状態や特定疾病)を満たした場合 |
| 給付上限 | 要介護度に応じて、上限が決定 | 契約内容により異なり、柔軟な上限設定が可能 |
| 利用者負担 | 原則1割~3割(所得によって異なる) | 保険金以外の費用は自己負担 |
| 保障の自由度 | 制度で定められたサービス利用のみ | 契約により、保障内容や給付方法、金額などを自由に設定可能 |
公的介護保険は、40歳以上の国民が加入する義務があり、要介護認定を受けた場合に、訪問介護や通所介護などのサービスを現物で受けられます。費用は原則1割~3割の自己負担で、残りは保険から支払われます。
一方、民間介護保険は任意加入で、保険料や給付内容は契約によって異なります。介護状態になった際に現金で一時金や年金形式の給付を受けられ、使い道の自由度が高いのが特徴です。
公的介護保険と民間介護保険は併用して利用することも可能なので、うまく組み合わせることで、将来の介護の経済的不安を軽減できます。
公的介護保険の申請方法

公的介護保険を利用するには、お住いの市区町村に対して申請を行い、要介護の認定を受ける必要があります。
以下に、申請の流れや具体的なステップについてまとめました。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.申請 | 市区町村の介護保険担当窓口に「要介護認定申請書」を提出します。 家族、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことも可能です。また、申請には介護保険被保険者証が必要です 。 |
| 2.認定調査、主治医意見書の作成 | 市区町村の職員(または委託された調査員など)が自宅や施設などを訪問し、心身の状態について聞き取りや調査を行います。 主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼し、病状や生活機能に関する「主治医意見書」を作成します。 |
| 3.審査判定 | 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、専門家で構成される介護認定審査会が要介護度を判定します。 |
| 4.認定結果の通知 | 市区町村から、審査結果が郵送されます。申請から認定の通知までは、原則30日以内に行われます。 |
| 5.サービス計画書(ケアプラン)の作成 | 要支援または要介護と認定された場合は、サービス計画書(ケアプラン)の作成を行います。 「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに相談します。 「要介護1」以上の介護サービス計画書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者に依頼が必要です。 |
| 6.サービス利用開始 | ケアプランに基づき、訪問介護や通所介護などのサービスが利用できます。 |
参考:厚生労働省「サービス利用までの流れ」
公的介護保険を利用するには、市区町村への申請からはじまり、認定調査や主治医意見書の作成を経て、介護認定審査会による審査判定を受ける必要があります。認定されたら、要支援または要介護の度に応じてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、介護サービスを利用が開始されます。
申請から認定までは、通常30日程度かかるため、介護が必要だと感じたら早めの申し込みが大切です。
公的介護保険を利用する際の注意点

公的介護保険は、高齢者の生活を支えてくれる重要な制度ですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。制度の仕組みを正しく理解していないと、必要な介護サービスを受けられない可能性もあるので注意が必要です。
ここからは、公的介護保険をスムーズに活用するために、事前に覚えておきたい注意点を解説します。
サービスを利用するには申請が必要になる
公的介護保険のサービスを受けるには、要介護認定の申請を忘れずに行う必要があります。介護保険は40歳以上から毎月保険料の支払いが発生しますが、公的介護保険の申請を行わないと、保険料だけ引かれ続けてしまいます。
また、公的介護保険の申請も承認まで一定の時間がかかるため、利用開始までの時間を考慮しておく必要があります。
介護の必要性を感じたら早めに相談や申請を行い、スムーズに支援を受けられるよう備えておくことが大切です。
利用できるサービスに制限がある
公的介護保険は民間介護保険とは異なり、利用できるサービスの範囲が決まっているため、必要な介護をすべて受けられるわけではありません。要支援1や2などの軽微な状態だと判定された場合は、主に介護予防を目的とした軽度のサービスが中心となり、重度の介護サービスは利用できません。
また、食費や住居費など公的保険の対象ならない費用もあり、これらは全額自己負担になります。
公的介護補家の不足を補うなら、民間介護保険との併用や自費サービスの活用を検討するのがおすすめです。
要介護認定の更新手続きが必要になる
公的介護保険の利用に必要な要介護認定は、一度認定されれば永久に有効になるわけではなく、更新手続きが必要です。要介護認定の有効期間は、認定申請日から新規の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月に設定されています。
更新には認定更新申請書や主治医の意見書の提出などが必要で、介護保険被保険者証が届くまでには一定の時間がかかります。
高齢の方が管理する場合は、うっかり期限を過ぎてしまう場合もあるため、家族の方などが市区町村からの通知に注意しておくことが大切です。
まとめ
公的介護保険制度は、40歳以上の国民が加入し、要介護認定を受けた場合に訪問介護や施設入所などのサービスを利用できる制度です。要支援や要介護度に応じた支給限度額が設定されており、自己負担額1〜3割で利用できます。
低価格で手厚いサービスが受けられる一方で、利用には市区町村への申請と認定手続きが必要で、申請から認定まで通常30日程度かかります。
これから公的介護保険を利用する可能性のある方は、サービス内容や保険料を確認して早めに準備しておくのがおすすめです。
「保険ほっとライン」では、保険に関するお悩みごとを無料でご相談いただけます。将来に備えて保険の加入をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問合わせください。
保険で困ったことがあれば、
何でもご相談ください
- 保険の相談実績20年で100万件以上
- 専門のスタッフが対応
最寄の保険ほっとラインの
店舗にて承ります。
お気軽にお問い合わせください。
ご予約はお客さまサービスセンターまで
0120-114-774
受付時間 10:00~19:00(土・日・祝もOK)
フリーワード検索
- 医療保険について
- 保険商品について
- 保険の種類
- 医療費の自己負担
- 医療保険の保障内容
- 介護保障保険について
- 個人年金保険と公的年金について
- 生命保険会社の個人年金について
- 公的年金保険について
- 火災保険・地震保険について
- がん保険について
- 自動車保険について
- 収入保障保険について
- 保険に関する豆知識
- 民間介護保険について
- 公的介護保険について
- 個人年金保険について
- 死亡保険金の税金について
- 学資保険について
- 賃貸物件の火災保険について
- 自動車保険の任意保険について
- ファミリーバイク特約について
- 原付バイクの任意保険について
- がん保険の必要性について
- 養老保険について
- ドル建て保険について
- 掛け捨て型の生命保険について
- 傷害保険について
店舗を探す